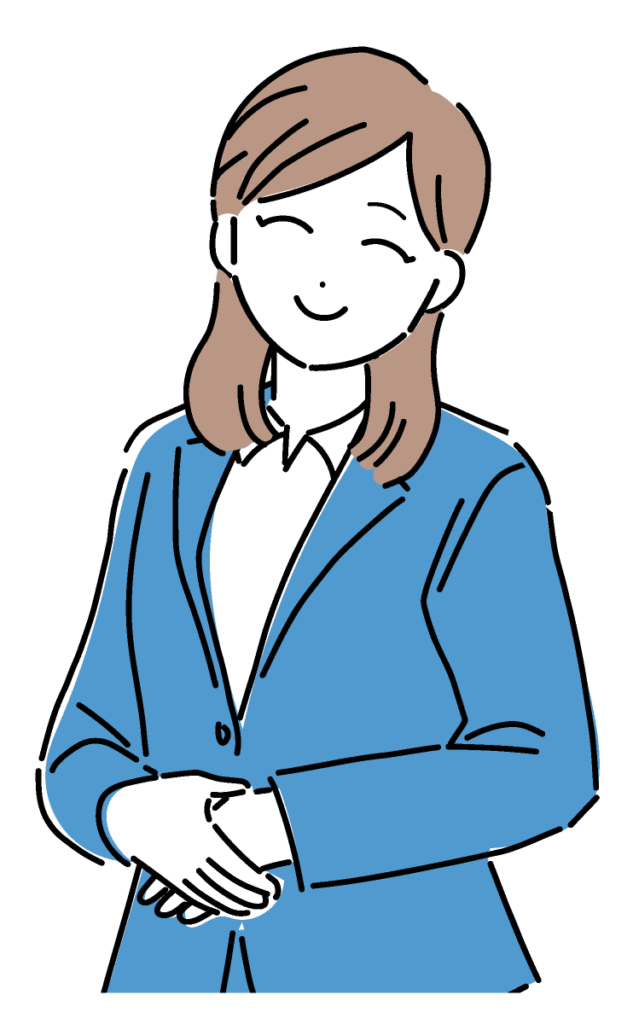こんにちは!本日はこちら!
思考停止してしまった子供の脳をもう一度はたらかせるには?
「問題を前にしてフリーズしてしまう…」
「考えようとしても頭が真っ白になる…」
「『わからない!』と言って、一つも問題に取りかかろうとしない…」
こんなお子さんの様子に悩んでいるお父様、お母様も多いのではないでしょうか?
勉強をしていると、子供が思考停止状態になってしまうことがあります。
特に、苦手な問題や初めて見る問題に直面すると、考えるのをやめてしまうことがよくあります。
しかし、大丈夫です!
子供の脳をもう一度働かせるための「声かけ」や「アプローチ」を工夫すれば、思考停止状態から抜け出すことができます。
今回は、子供の思考をもう一度動かすための具体的な方法をご紹介します!
1. そもそも、なぜ子供は思考停止してしまうのか?
まずは、お子さんが思考停止に陥る原因を知ることが大切です。以下のような理由が考えられます。
① 難しすぎて、どこから手をつけていいかわからない
- 問題が自分のレベルに合っていないと、手も足も出なくなる。
- 「これは自分にはできない」と思い込んでしまい、最初から考えるのをやめてしまう。
② 失敗を恐れている
- 「間違えたらどうしよう」「間違いたくない!」と思うと、考えが止まってしまう。
- 完璧主義の子ほど、正解が見えないと手を動かせなくなることがある。
③ 考え方のパターンがわからない
- 問題の解き方の「最初の一歩」がわからないと、思考が停止しやすい。
- どこから考えればいいのか、ヒントがないと手を出せない。
④ そもそも集中できていない
- 勉強に対するモチベーションが低い。
- 他のことが気になって、問題に意識を向けられない。
⑤ 脳が疲れている
- 長時間勉強していたり、学校や塾で頭を使いすぎると、脳が処理能力の限界に達してしまう。
- 疲れていると、考えを巡らせるエネルギーが残っておらず、簡単な問題でも「もう無理!」となりがち。
- 睡眠不足や栄養不足も影響し、思考力が低下する。
特に「脳の疲れ」による思考停止は、単に考え方を変えるだけでは改善しません。
30秒だけ目を瞑ってみよう!とか、適度な休憩やリフレッシュが必要になります。
2. 思考停止状態から抜け出すための具体的なアプローチ
① 「何が書いてあるんだっけ?」と聞いてみる
✅ 目的:考えるきっかけを作る
- 子供が「わからない」と言ったら、すぐに教えるのではなく、「何が書いてあるんだっけ?」と聞いてみましょう。
- 問題文をそのまま読むだけでも大丈夫!ここはブレインストーミング。どんどんリストに上げていきましょう。
- 問題文を音読させたり、図やグラフを見せたりして、まずは情報を整理させることが重要です。
🔹 例
子供:「この問題、わからない…」
親・先生:「問題文に何が書いてある?」
子供:「えっと…『りんごが3個、みかんが2個あります』って書いてある」
親・先生:「じゃあ、問題文の最後では、何を求めてとあるかな?」
こうすることで、子供が問題文を自分で読み直し、考えるきっかけを作ることができます。
② 「どうしたら楽しくできる?」と聞いてみる
✅ 目的:前向きな気持ちで取り組めるようにする
- 勉強が「つまらない」と感じると、考えるのをやめてしまいます。
- 「どうしたら楽しくできる?」と聞くことで、勉強への姿勢を変えることができます。
- 脳が一番能力を発揮するのが”楽しいとき”です。勉強もどんどん楽しんでしまいましょう!
🔹 例
子供:「この年号の問題、多すぎて嫌だ…」
親・先生:「じゃあ、どうしたら楽しくできるかな?」
子供:「うーん…タイマーで競争してみる?」
親・先生:「いいね!じゃあ、3分以内にできるかチャレンジしてみよう!」
このほかにも社会なら年号の語呂合わせ、国語なら面白い例文作り
理科は化学式や計算式の覚え方、英語なら好きな芸能人などのインタビュー動画の一部を使うなど
様々な方法があります。
このように、子供自身に「楽しくする方法」を考えさせると、勉強に前向きになりやすいです。
③ 「どこまでならわかる?」と質問する
✅ 目的:「できる部分」を見つけて、自信を取り戻させる
- 思考停止してしまう子供は、「わからない」という気持ちが先行し、できる部分まで見えなくなっています。
- 「どこまでならわかる?」と聞くことで、考えられる部分を探し出し、解決の糸口を見つけます。
🔹 例 子供:「この文章題、全然わからない!」
親・先生:「じゃあ、どこまでならわかる?」
子供:「うーん…登場人物が3人いるのはわかる。」
親・先生:「そうだね。じゃあ、この人たちがそれぞれ何をして、どんな気持ちなのか整理してみよう。」
場合によっては表や絵を使いながら、今わかっているところまでを整理します。
そこから、少しずつ考えるポイントを見つけることで、思考が再び動き出します。
④ 「どうしたらいいと思う?」と聞く
✅ 目的:間違えた問題を自分で解決策を考え、定着させる
- 間違えた問題を訂正する時に「次、間違えないためにはどうしたらいいと思う?」と聞く
- 「教えてもらう」ではなく、「自分で考える」力を育てることが大切です。
🔹 例 子供:「この漢字、全然覚えられない…」
親・先生:「どうやったら覚えられると思う?」
子供:「うーん…意味とか調べるといいかな?」
親・先生:「いいね!じゃあ、この漢字が使われている熟語や漢字自体の意味を調べてみよう!」
子供自身に「解決策を考えさせる」ことと、教師や保護者のプラスアルファの声かけで、主体的に学ぶ力が育ちます。
⑤ 脳の疲れをとる
✅ 目的:思考力を回復させる
- 長時間の勉強で疲れている場合は、適度に休憩を取らせる。
- 「ポモドーロ・テクニック」(25分集中+5分休憩)など、時間管理の工夫をする。
- 体を動かしたり、軽くストレッチをさせると脳が活性化する。
- 夕方以降の勉強なら、甘いものや温かい飲み物をとるとリラックスしやすい。
3. まとめ|「考えられる子」に育てるために
思考停止してしまった子供の脳をもう一度働かせるためには、すぐに答えを教えるのではなく、考えるきっかけを作ることが大切です。
✔ 子供の思考を動かすための質問
- 「何が書いてある?」 → 問題を整理する
- 「どうしたら楽しくできる?」 → 勉強を前向きにする
- 「どこまでならわかる?」 → できる部分を探す
- 「どうやったらできるようになると思う?」 → 解決策を考えさせる
- 「ちょっと休憩しようか?」 → 脳の疲れをリセットする
このような声かけを続けていくと、「すぐに諦める子」から「自分で考える子」へと成長していきます。
余談ですが、先日小学6年生の国語の授業で『考えることを考え続ける』という単元がありました。
その中で、「あなたにとって考えるとはどんなことですか。」という問題がありました。
大人の皆様どうでしょうか?考えるってどうすることなのでしょうか?
いざ、説明してと言われると難しいですよね。
そこで小学6年生の生徒さんが出した答えが『頭の中で、想像したり、いろんなことを思うこと』でした。
思考停止してしまう生徒さんの中には、インプット過多で、自分の中で反芻する時間を持てないという方が
少なくありません。
もちろん知識がなければ想像することもできないわけなので、インプットは前提としてありますが、
得た知識を想像する、想いを巡らせる…その機会を、声かけによって大人がアプローチしてあげると
考える能力もグッと高くなるはずです。
間違っても『ちゃんと考えなさい!』ではお子さんは動かないばかりか、
さらに、思考停止が悪化してしまうのでご注意を!
お子さんが自分で考え、学ぶ楽しさを感じられるように、ぜひ取り組んでみてください!
Lupinustでは会話・対話を中心としたマンツーマンの授業が可能です。
・集団授業についていけるか自信がない…
・周りの目が気になってなかなか質問できない
・マンツーマンで細かいところまでじっくり教えてほしい!
・不登校で学校の進度に追いつけないことは心配
など、お困りの方はぜひ一度お気軽にご相談ください。
初回のカウンセリングは無料です。
下記の公式ラインよりお申し込みください。
公式ライン: